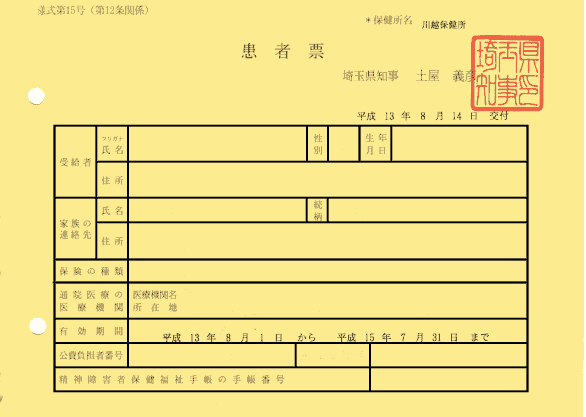
精神保健福祉法32条に、ついては本文にも書いたが、こまごまとした手続きについて、あまり詳しく書かなかったので、別項としてまとめてみる事にしました。
注意:本稿は記録の整合性のため残してあります。精神保健福祉法32条は2006年3月末で廃止されました。
基本的には、「うつ病」を含む、精神障害で通院加療が必要な人は、すべて対象者になります。精神障害の度合いによって、適用されない場合もありますが、その病気が「重い」「軽い」は、患者が判断するものではなく、医師が判断するものです。
うつ病、抑うつ状態と診断されたら、「精神保健福祉法32条」の申請ができるかどうか、医師に尋ねてください。
基本的には、申請用紙を市町村の受付窓口(2002年4月に都道府県の保健所が、扱っていた業務が、市町村が扱うよう改正された)にとりに行き、医師にその書式に従った診断書を書いてもらい、再び、受付窓口に持っていくのですが、医療機関がすべての手続きを代行してくれる場合があります。この場合は、認印を押すだけなので、あらかじめ持参したほうが手間が省けます。申請、更新には、2000円かかります。
まずは医師に聞いてみましょう。
認定を受けると、患者票が発行され、精神障害の医療にかかる費用の95%が、支給され、本人負担分は、5%だけになります。
うつ病は、仕事を続けるのが困難になったり、極端に作業能率が悪くなったりで、それまでの仕事をしばらくの間休職し、治療に専念しなければならないこともあり、収入が減ったり、雇用保険から支給される、休職中の支給(基本給の60%)になったりするので、医療にかかる費用が、このように大幅に減少する制度は使わない手はないと思います。なお、実際の負担は、都道府県により、異なります。
以前は、都道府県の保健所がこの事務を行っていましたが、現在は、市町村の機関が行うよう変更になっています。
この制度を利用する場合、医療機関を1つにしなければいけません。別の医療機関に転院するときは、医療機関に預けてある「患者票」を返却してもらい、保健所に持っていき、変更手続きをしなければなりません。
この場合、「手続きをした日」より、新規に選定した医療機関に適用されますので、それまで、通院していて、患者票を受けとり、その足で、保健所に申請した場合、その日の通院には、適用を受けられなくなってしまい、差額を支払いに行かねばなりません。
逆に、患者票を受けとり、手続きをとらずに、新規の医療機関で、治療を受け、その日のうちに、市町村の申請窓口に行き、変更手続きをした場合、新規の医療機関で支払うのは、治療を受けた時点では、健康保険のみが有効なので、5%にはなりませんが、32条適応になるため、次回診療時に、その差額が戻ってきます。
この制度を利用できるのは、認定を受けてから2年間です。
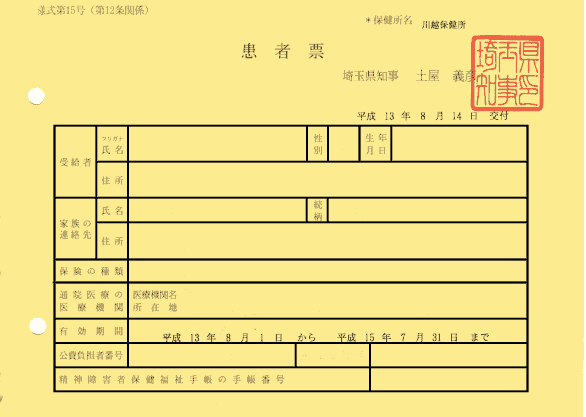
しかし、それまでに完治しなかった場合、再申請して延長することができます。
Copyright © 2003 
All rights reserved.